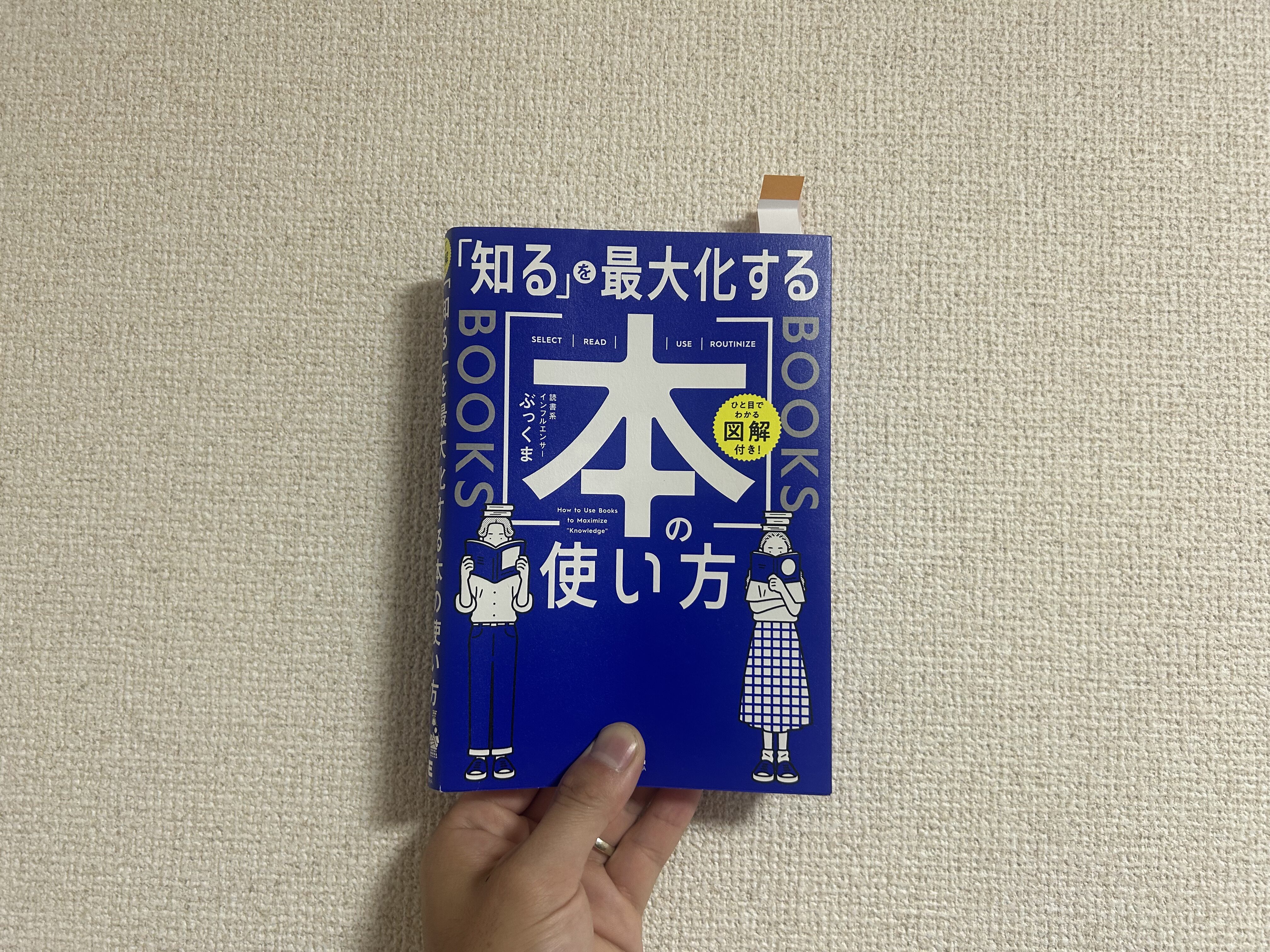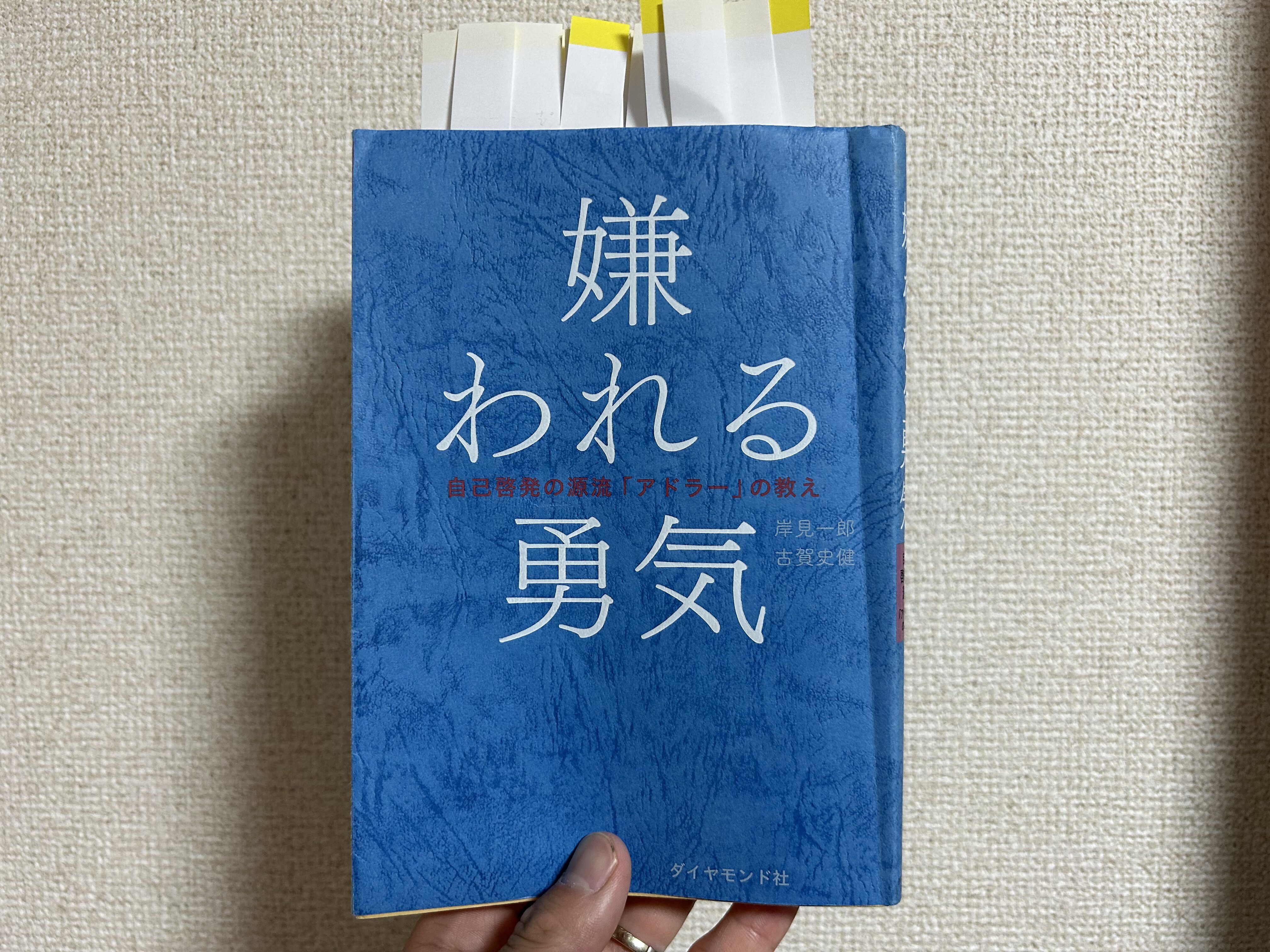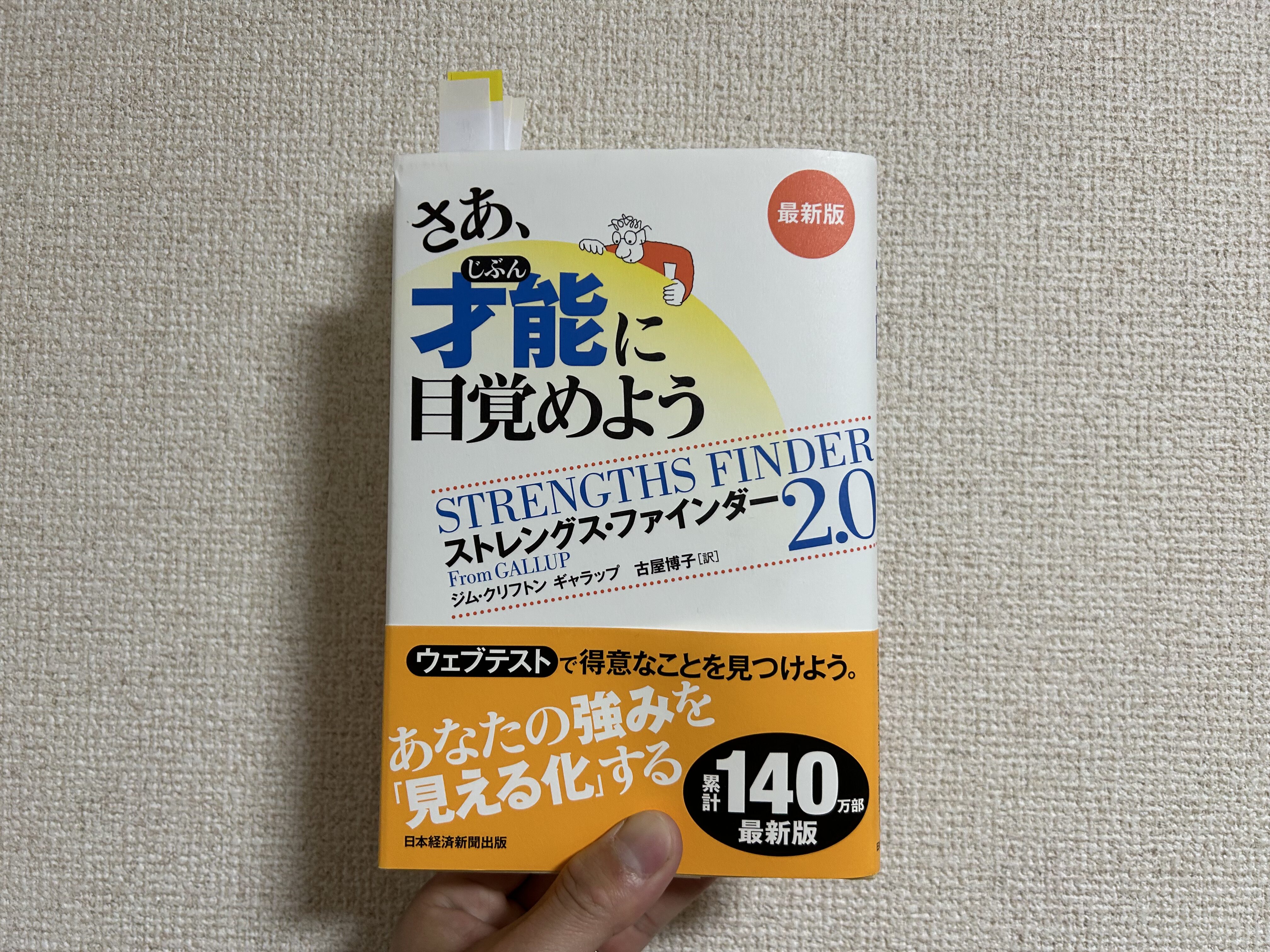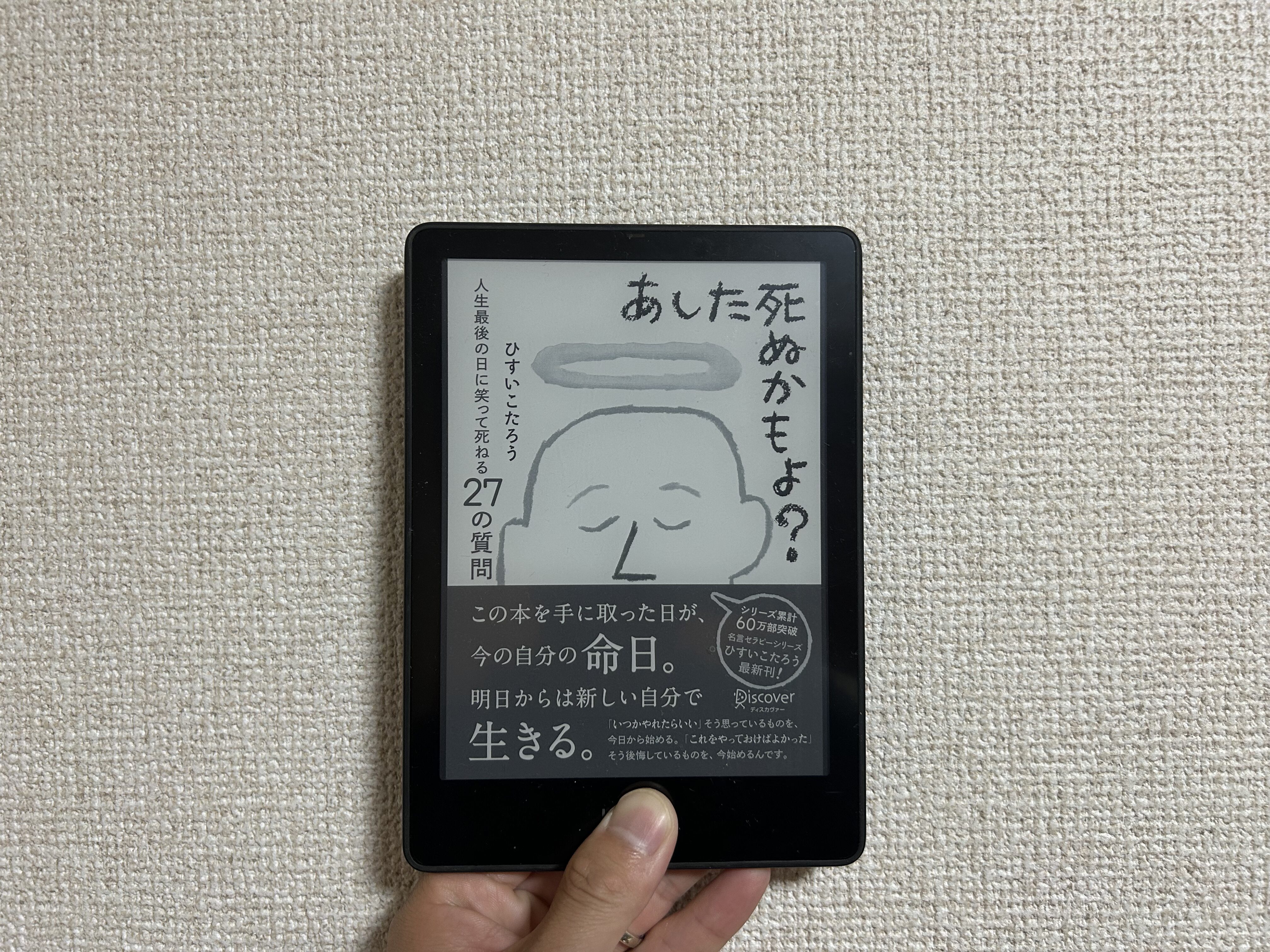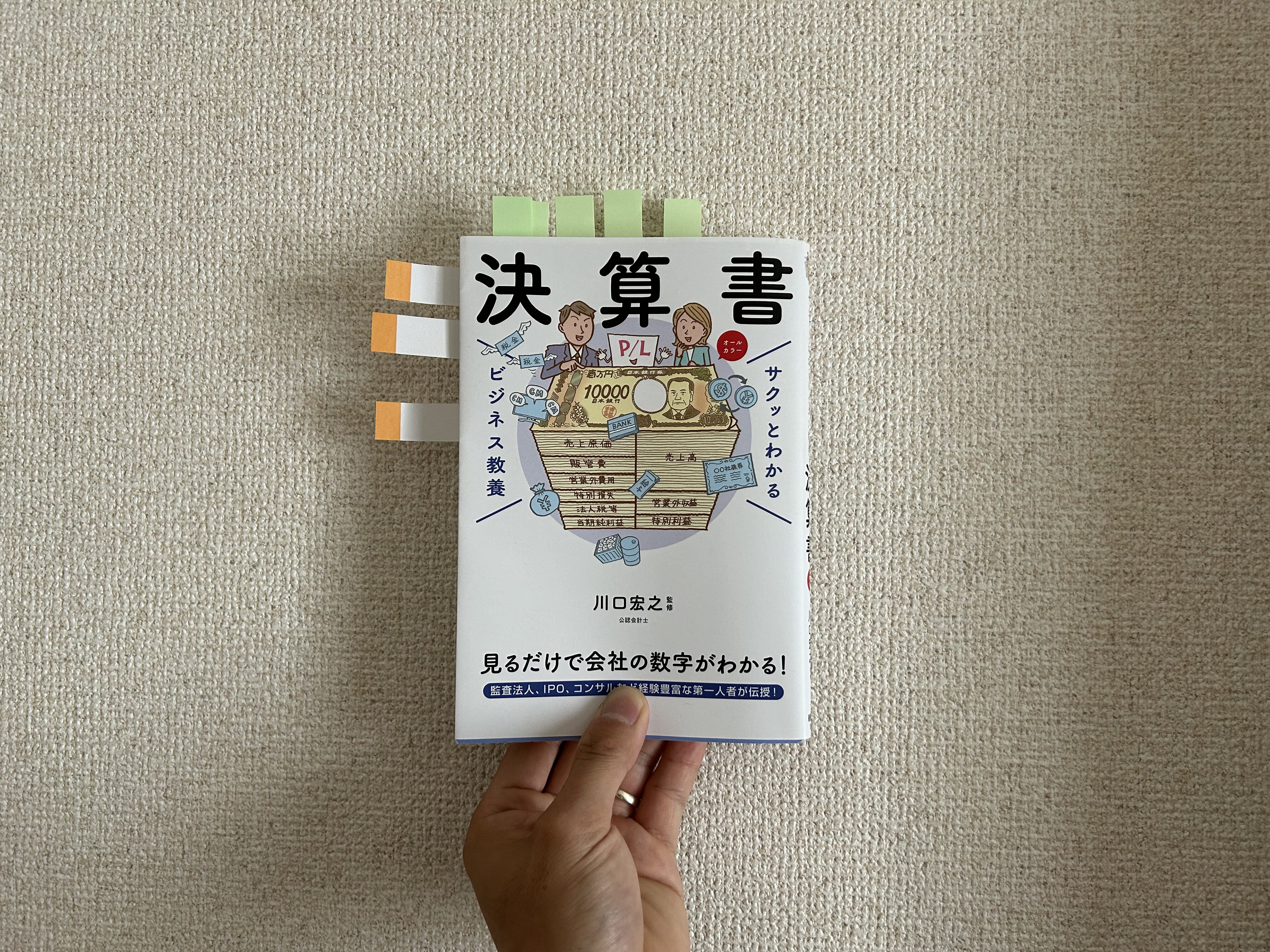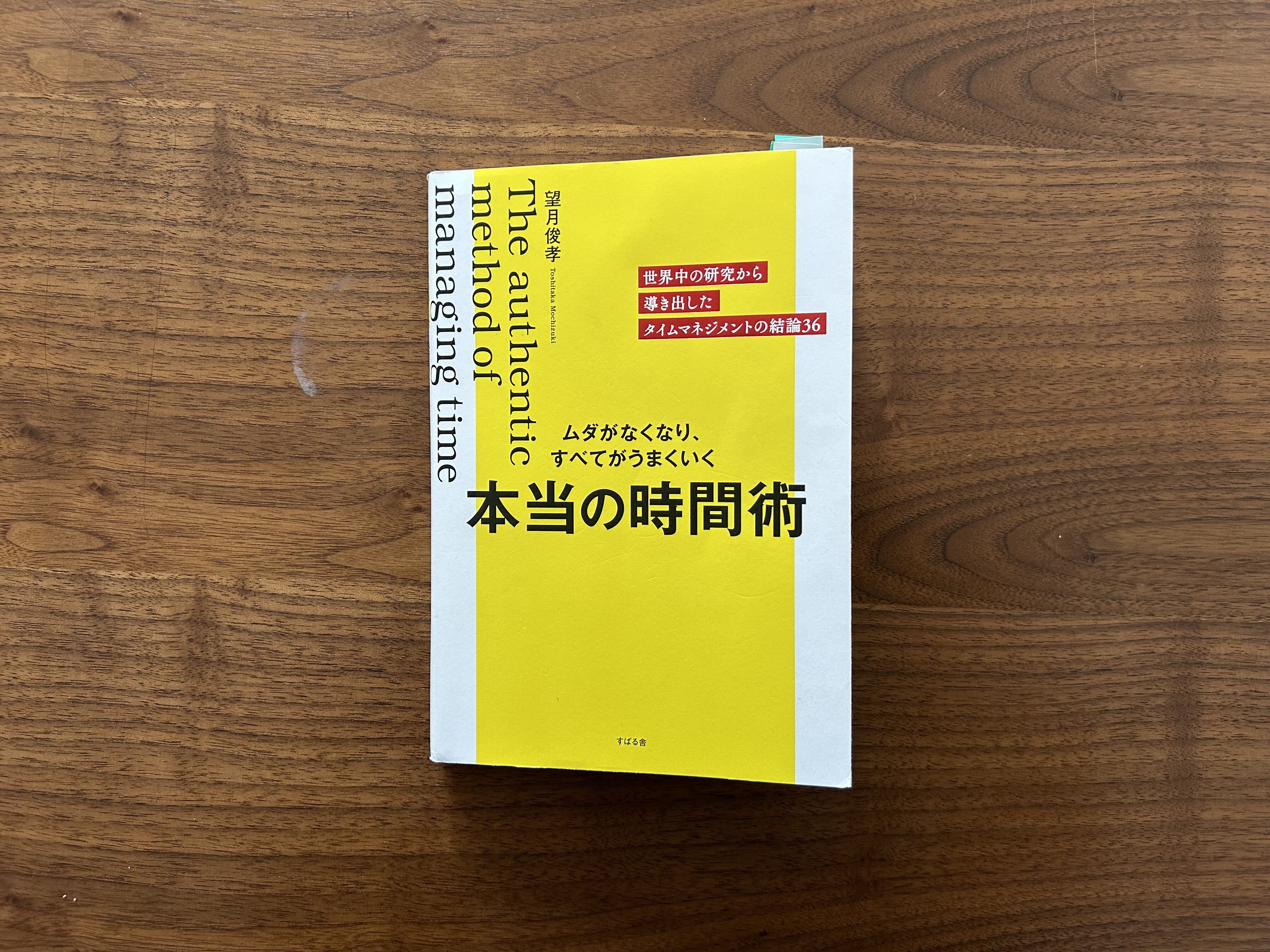老舗を再生させた十三代がどうしても伝えたい 小さな会社の生きる道。
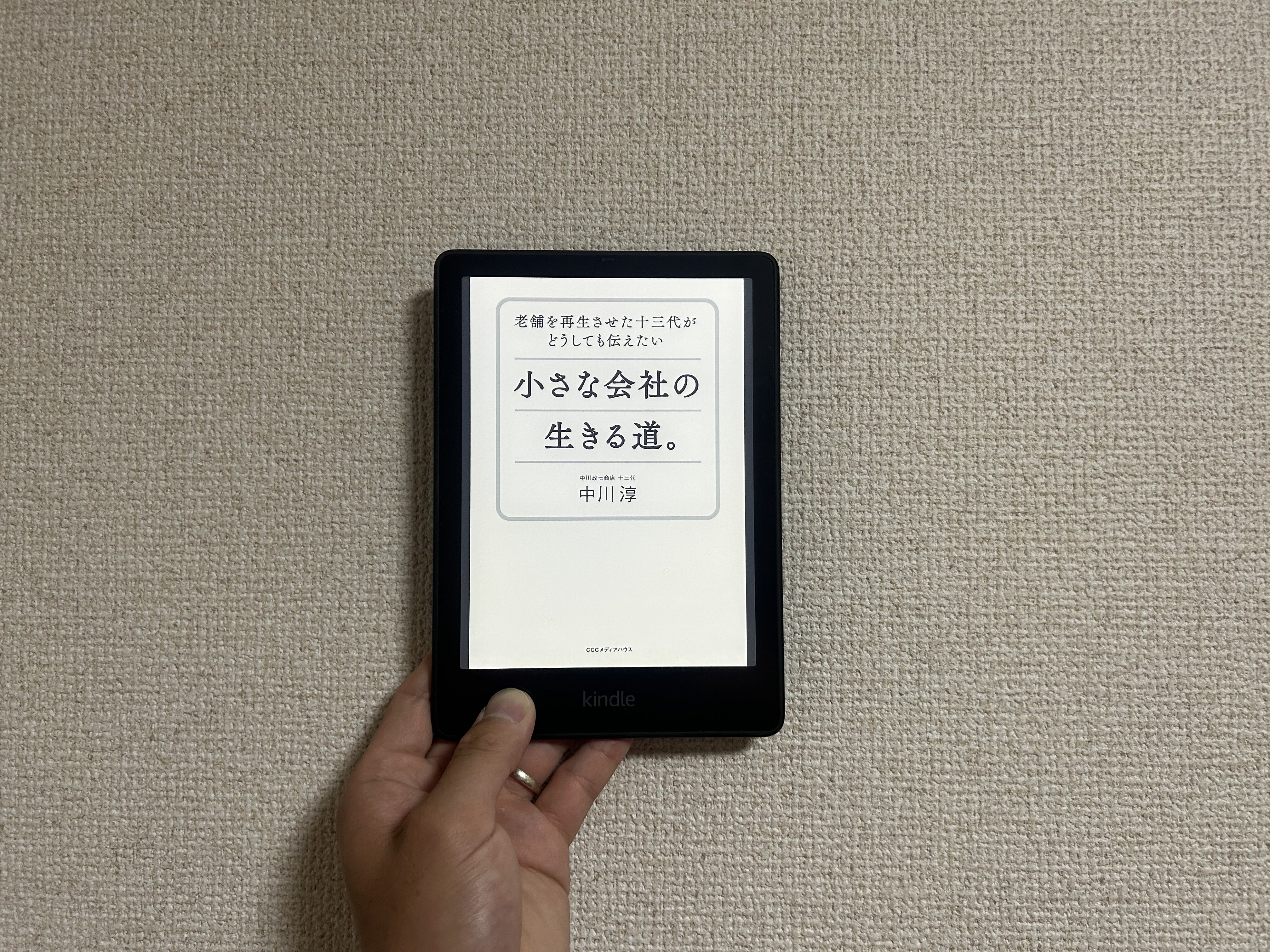
読んだ目的
・以前読んだ「小さな会社のおおらかな経営」で本書の著者である中川淳さんの「デザイン経営」に対する考え方が書かれていて、より知りたいと思ったから
・業種は違うが、小さな会社のコンサルティングの現場を知ることで、家業(設備屋)に活かせることがあるんじゃないかと思ったから
・単純に、ブランディングに興味があったから
要約
本書は、ものづくりの会社がブランドを築き上げていく過程や、そのために必要な考え方を紹介しています。
第1部では、小さな会社のコンサルティング事例が時系列で紹介されており、どのようなプロセスでブランドが構築されていったのかを具体的に知ることができます。ブランドづくりの現場感が伝わり、実務に役立つヒントが多く含まれています。
第2部では、ものづくり企業に必要な経営の考え方が解説されています。プランを立てて進めることも重要ですが、それ以前に会社の基本的な経営体制をしっかり整えることの大切さが強調されています。経営の土台作りの重要性を改めて認識できる内容です。
心動いた部分と感想
会社のビジョンについて
どんなブランドをつくりたいか、どんな会社になりたいか、社員みんなに聞いたが、漠然とした議論になってしまい要領を得ない。これが一番の問題かもしれない。(p15)
まさに今の家業もこの状態。自分自身、「ワクワクする場所にしたい」というイメージはあるけど、具体的な事業ビジョンには落とし込めていない。
現状認識から始まりビジョンを定めてより具体的な「ゴール」を描くことで、会社全員でビジョンとそこに向かう「熱」を共有することができる。(p215)
目の前の予算達成がすべてではなく、その予算達成が何につながっているのか、なぜ必要なのかを全スタッフが理解できる。(p215)
会社にとって最も重要なのはビジョンである。ビジョンのない会社は存在意義がない。(p216)
経営者が本当にやりたいことを掘り下げることで、ビジョンが見えてくる。自分たちがどうなりたいか(will)、自分たちに何ができるか(can)、自分たちは何をすべきか(must)。この三つが重なり合う部分こそがビジョンになりえる。(p217)
自分たちが「どうなりたいか(will)」「何ができるか(can)」「何をすべきか(must)」。この三つの重なりを考えていきたい。
筋の良い組み立てとはどういうことか?簡単に言うと雑誌が取り上げたくなるような、一般の人が説明を聞いて「へぇ~」となるようなストーリーがあること。(p27)
納得感って、ストーリーと順序がちゃんとしてる時に生まれるもの。確かに、買いたくなる。
実際どうかはわからない。しかし仮説を立てることで、一年後にはより精度の高い仮説を立てることができる。(p30)
取り合えず考えて、仮説を立てることが大事なんだと思った。積み上げていかないと何も残らない。
何事も大きなところを考えてから、小さなところを決めていくのが原則。いきなり小さいところから入っては、商品政策が積み上がっていかない。(p41)
細部から入ると、いつまでたっても全体像が見えない。自分がいつもやってしまいがちなこと。「全体から部分へ」が大原則。
つくり手にとって、捨てるのは苦痛かもしれないが、自分たちにとっては当たり前のことが必ずしも通じないということを理解しなければならない。言いたいことを極限まで絞り込む。多くても三つまで。(p162)
メッセージに優先順位をつけるときに大切なのは、こちら側がどのメッセージを一番に伝えたいかよりも、どのメッセージが一番お客さんに響くかである。(p260)
今まで何度もやってきたが、絞り込むって本当に難しい。でも、伝えるには避けて通れない。
経営とは会社の状況を正確に把握し、必要な施策をしかるべき順番で実行することである。状況把握が正確にできれば、問題の七割は解決したに等しい。(p209)
状況を把握することはそれだけ大事だということ。逆にいえば多くの企業が状況を正確に把握できてない。まず家業でそれができるようになりたい。
コンサルティングするときに、必ずつくってもらう「三種の神器」がある。・グランドデザイン・中期経営計画書・年間スケジュール(p214)
「神器」と言われるくらい計画を立てることは大事だということ。家業の現状では、繋がりのある元請けから仕事をお願いされ、見積りして現場をこなす。特に営業もしていない。それでも成り立ってしまっている。計画を立ててないから、会社自体が良くなっていくこともない。
最大のポイントは、お客さんの視点で考えること。お客さんにとって価値のあるものにつながる強みであるか。「自分」の定義も、お客さんにとってその会社、ブランドがどのように見えるかにかかってくる。(p240)
内側から見た「良さ」と、外から見た「魅力」は違う。外からの視点、大事にしたい。
たとえあったとしても、それを世間の人が知らなければ、それは差別化されているという認識でなんら問題ない。世間が知らないということは「ない」と同義である。(p241)
「伝える努力」をしないと、存在していないのと同じなんだなと痛感した。
この本を読みながら、ぼんやりとしていたビジョンが、少しずつ輪郭を持ち始めた気がします。
「自分たちはどうなりたいか」─まずはそこから、言語化してみようと思います。